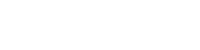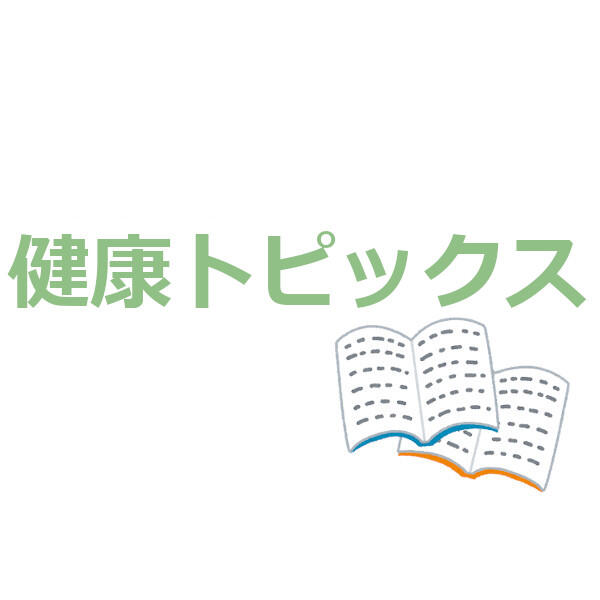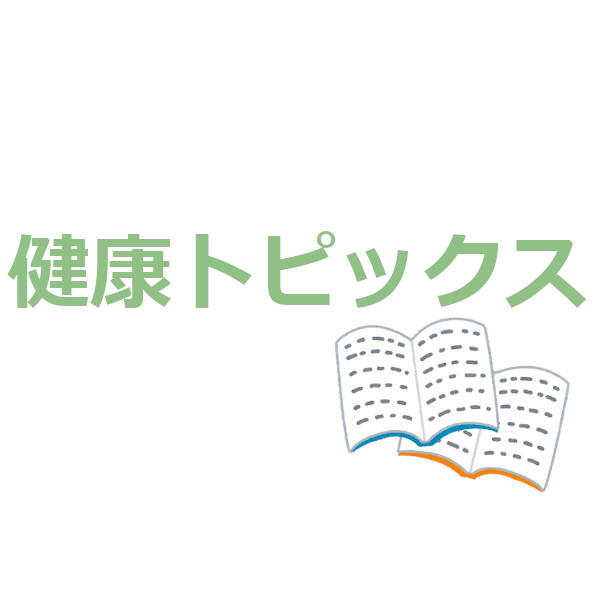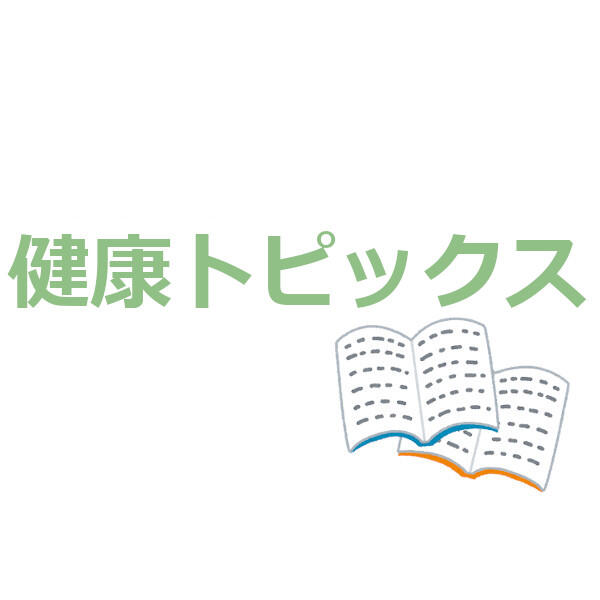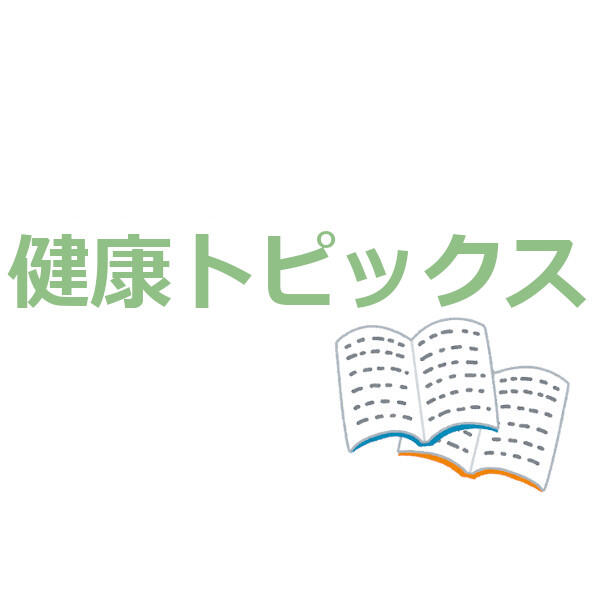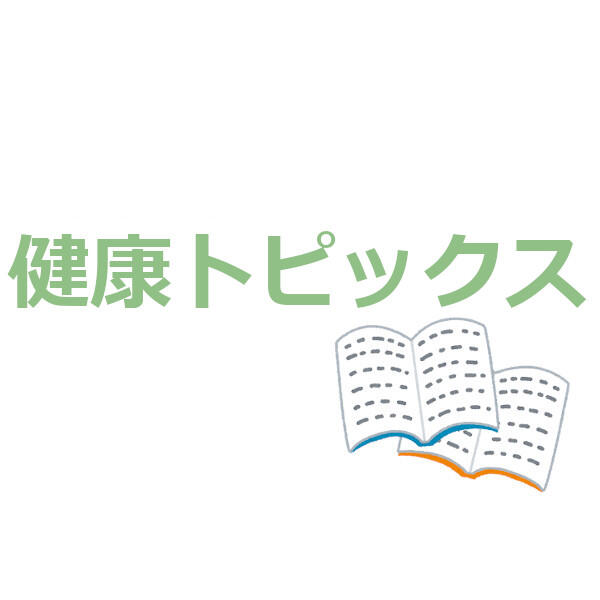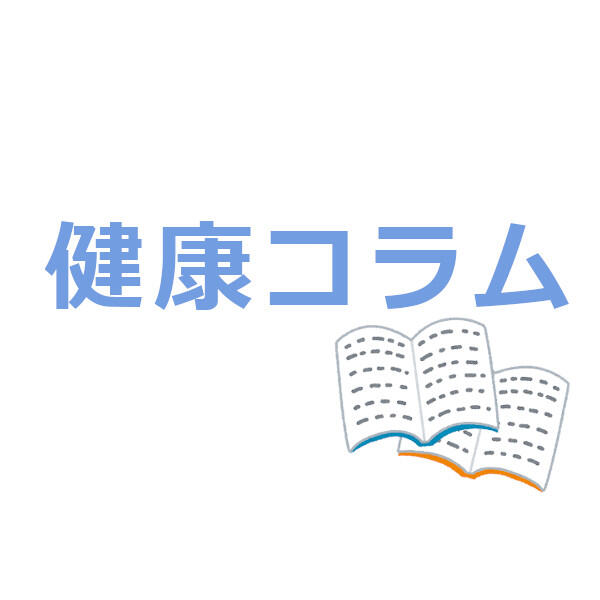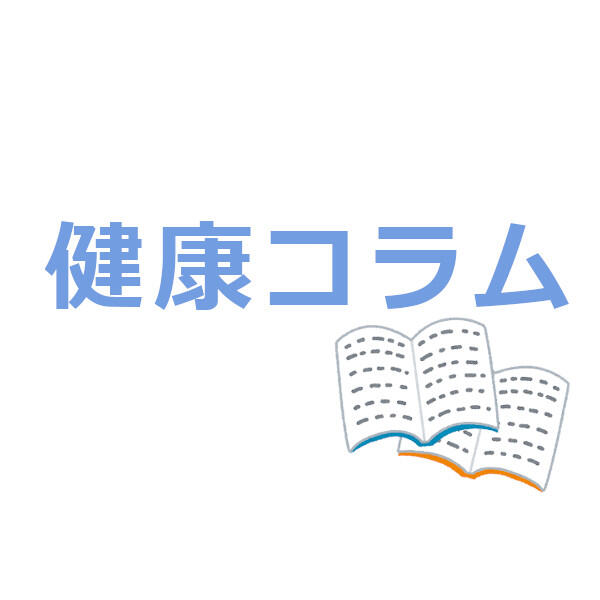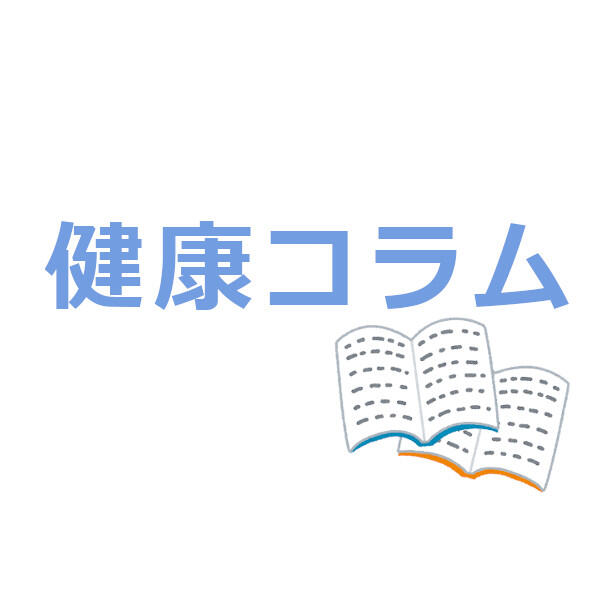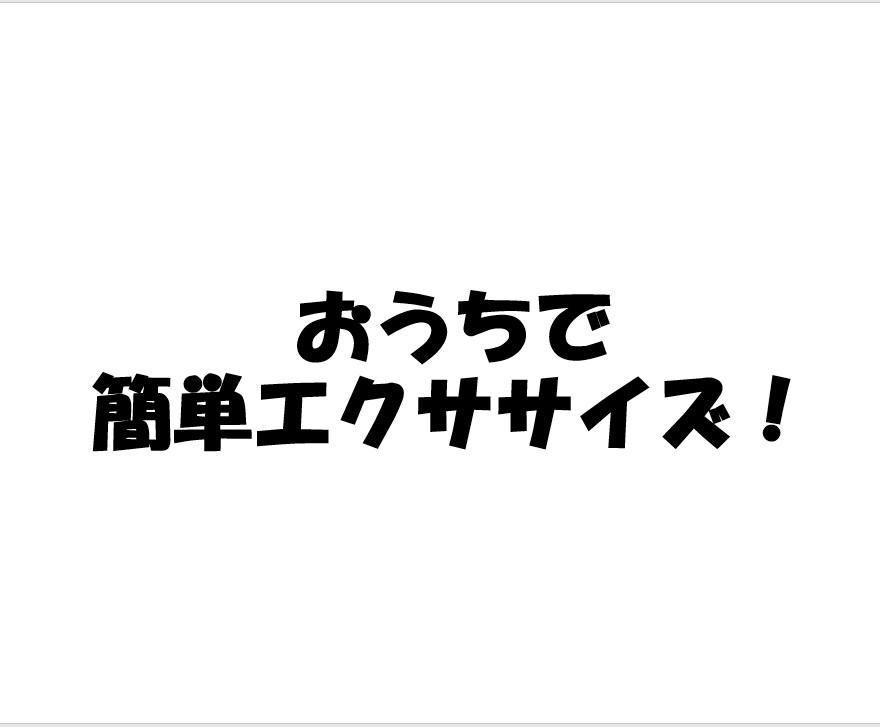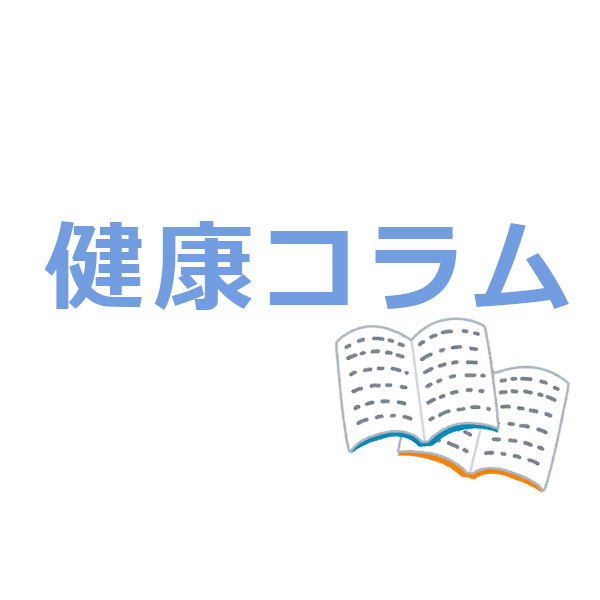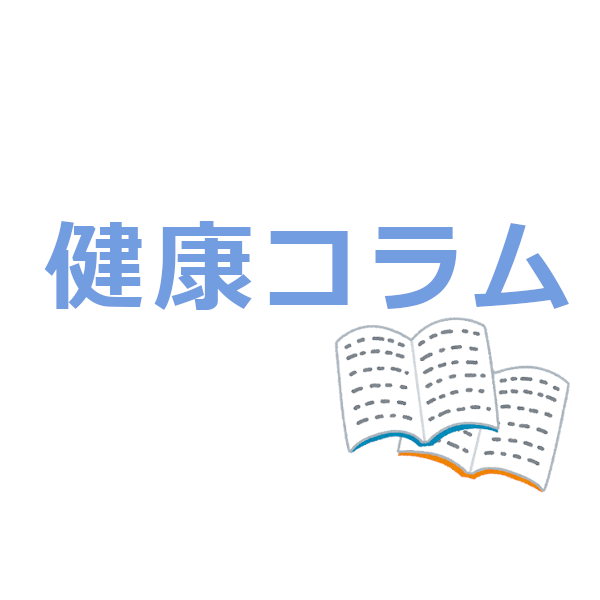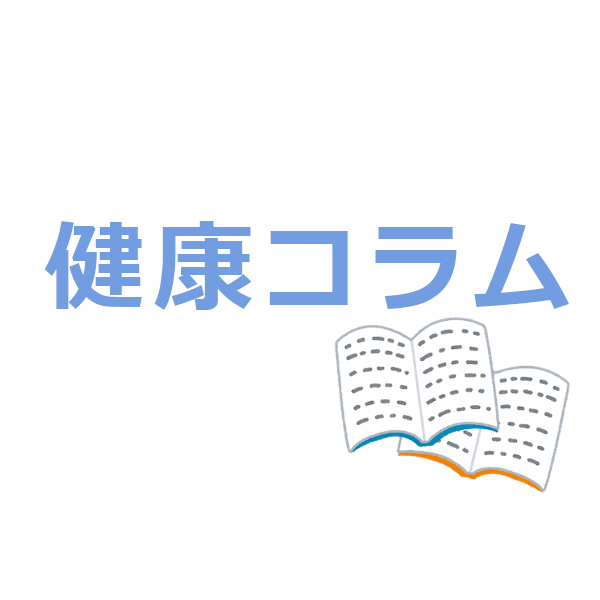-
- 低血圧ってどういう状態?
- 低血圧の4つのタイプ
- 日頃からできる改善策は?
めまいやふらつきがあったり、体がだるくて朝起きるのがつらい...といったことが続く場合は、「低血圧」が原因かもしれません。
春になり気温が上昇すると、血圧は下がるといわれています。そのため、この時期にとくに不調があらわれてしまう方も多いのだとか。
よく聞く言葉だけど、意外と知らない「低血圧」のこと。今回は、そのタイプや症状、対策などをご紹介します。
低血圧ってどういう状態?
低血圧の基準
高血圧には、"収縮期血圧140mmHg以上 かつ/または 拡張期血圧90mmHg以上"という、「日本高血圧学会」が定めた基準値があります。
一方、低血圧は日常に支障がなければ心配する必要はないとされ、つらい症状に悩まされる場合にはそれぞれの症状に合わせたケアが望まれています。
これは高血圧のほうが、生死にかかわる重大な疾患につながる可能性があり、問題視されやすいため。低血圧に関しては血圧が低い=病的な状態であるとは限らないと考えられ、対策が遅れているという現状があるのだとか。
海外では、低血圧の基準を収縮期(最高)血圧が90mmHg以下、拡張期(最低)血圧が60mmHg以下としている国も。ひとつの目安としておきましょう。

症状は?
全身の倦怠感をはじめ、めまいや立ちくらみ、食欲不振などが主な症状です。
そのほか、頭痛や肩こり、不眠、胃もたれ、吐き気、発汗など、その人によって現れ方は様々です。
めまいなどの症状から貧血と似ていると思われがちですが、貧血は血液中の赤血球やヘモグロビンが減少している状態。一方、血圧は血液が血管壁を押す圧力を示すものであり、低血圧とはその力が弱い状態といえます。
低血圧の4つのタイプ
【1】本態性低血圧
低血圧の中でもっとも多いのが、原因がはっきりしていない「本態性低血圧」で、低血圧症といわれる方の9割がこれに当てはまるのだとか。
病院では、血圧が慢性的に低いこと、そして症状が出ていてもほかに病気の可能性が見当たらない場合に診断されることが多く、体質によるもののほか、遺伝の可能性もあるとされています。
【2】起立性低血圧
急に起きあがったり立ち上がったときにフラッとするのが、「起立性低血圧」です。動く前と後の最大血圧を比べて20mmHg以上下がっていると、これに当てはまります。血圧の下がり幅によって起こるため、普段低血圧状態でない方や、高血圧の方でも一時的に症状が現れることがあります。
また、自律神経が関わっている場合も。血圧を調整する自律神経が正常にはたらかなくなると、下半身にたまった血液が心臓に戻りにくくなります。それにより脳の血流量が減少し、ふらつきなどを感じることがあります。
【3】食後低血圧
食事のあとにふらっとすることが何度もあった場合は、食後低血圧かもしれません。
これはその名の通り、食後に急激に血圧が下がる症状のことです。消化のために胃に血液が集まり、心臓に戻りにくくなることで起こります。人によっては、強い立ちくらみで失神を起こしてしまうことも。
欧米などの例から、高齢者の3人に1人がなるともいわれ、加齢によって誰でも起こり得るものといえます。
また最近では、食後低血圧が脳卒中や心筋梗塞などを引き起こす、という可能性も指摘されています。「おかしいな」と思ったら、早めに対策をはじめましょう。
【4】症候性低血圧
病気の症状として低血圧が起こることもあります。心筋梗塞や不整脈などの心臓疾患、胃腸の疾患による栄養不足、降圧剤や抗うつ薬などによる副作用、大きなケガによる出血など、その原因は様々です。
日頃からできる改善策は?
食生活の見直しポイント
低血圧の方は、食欲不振などであまり食事が摂れなかったり、朝起きられずに朝食を抜くことが多い傾向にあるため、栄養バランスは偏りがちに。3食の中でも朝食は血圧を上昇させるための大事なエネルギー源です。1回ごとの量より、1日3回きちんと食べることを意識しましょう。
肉・魚・大豆などに含まれるたんぱく質をしっかり摂ること、また塩分をきちんと摂ることも大切です。塩分は血管を収縮させ、血圧を上昇させるはたらきがあります(ただし、塩分は高血圧の原因にもなりますので、摂りすぎには注意が必要です)。
一般的に低血圧の方は疲れやすいため、塩分と疲労回復に有効なクエン酸がまとめて摂れる"梅干し"を一緒にとるのもよいですね。
また、ビタミンや塩分以外のミネラルもバランスよく摂りましょう。野菜や海藻類も積極的に。水分もたっぷり補給してくださいね。
●食後低血圧が心配な場合には...
消化による急激な血圧低下を防ぐため、1回の食事量を少なくして回数を増やすのも方法です。早食いせずゆっくり食べることも意識しましょう。

寝起き・食後はゆっくりと
起立性低血圧の人は、めまいなどを予防するために、睡眠時には枕などで頭をやや高めにしておきます。起床時は、足首を動かすなど血液のめぐりをよくしてから、ゆっくりと起き上がりましょう。
食後低血圧の場合は、すぐに動こうとするとめまいなどによって転倒するキケンも。これを防ぐためには、食後1時間以上はしっかりと休息をとりましょう。
血液のめぐりをよくする運動を
一般的に低血圧の人は、足や手の血管の収縮力が弱く、血液の循環が悪くなりがち。それにより、脳の血液量が足りずにふらつくなどの症状が出やすくなります。
足のめぐりをよくするには、太ももやふくらはぎの筋肉を刺激するのが効果的です。ウォーキングや階段の上り下りなどがおすすめ。動悸や息切れを起こしやすい人もいるので、早歩きではなく、散歩のようにゆっくりと歩きましょう。
手のめぐりをよくするには、手を握ったり開いたりするグーパー運動をくり返し行うのも効果的。30〜50回を目安にしてみてくださいね。
低血圧は、体質などによるものも多いと考えられていますが、食生活や普段の行動などを意識し変えていくことで、症状が改善することも。
上記のような対策をしていても変化がなく、症状がつらい場合には、早めに医療機関を受診しましょう。
- 通話料無料 0120-575-368(日曜、祝日を除く9時〜20時)
- 医師・薬剤師・栄養士から構成される専門スタッフが、医薬品、医薬部外品、健康食品について飲みあわせを含めて、ご質問・ご相談を承ります。