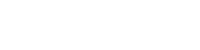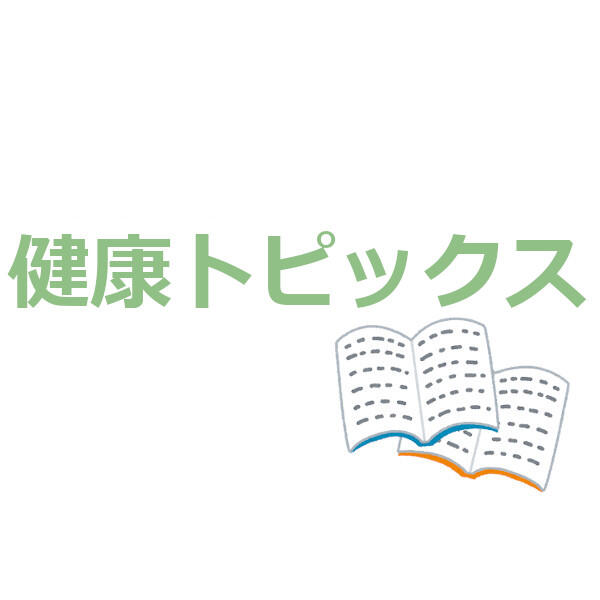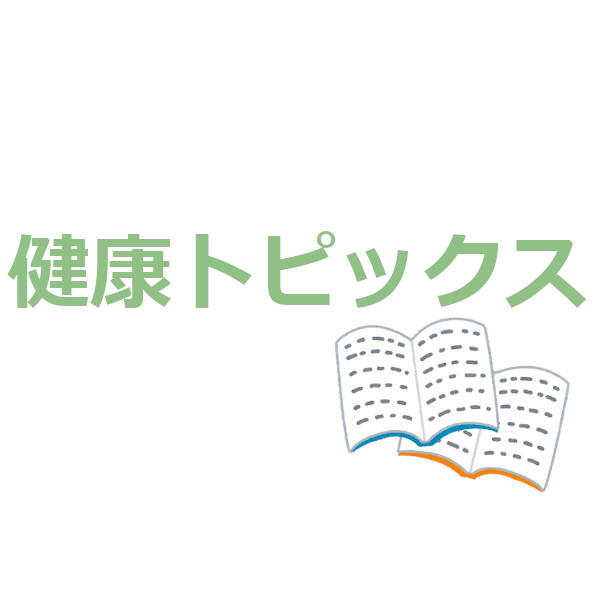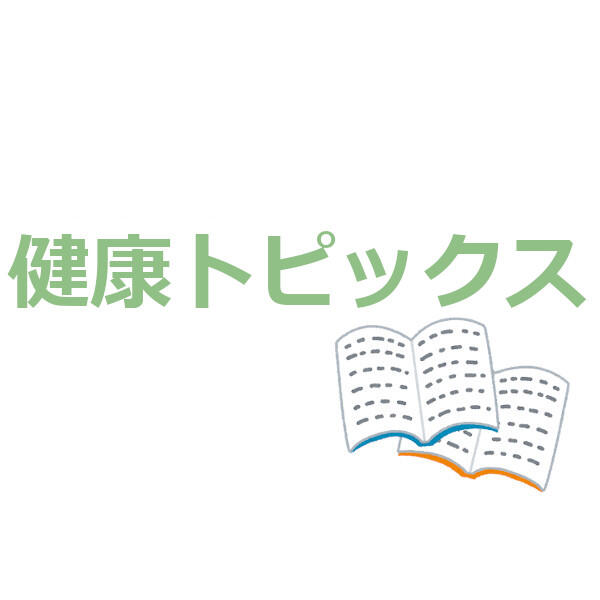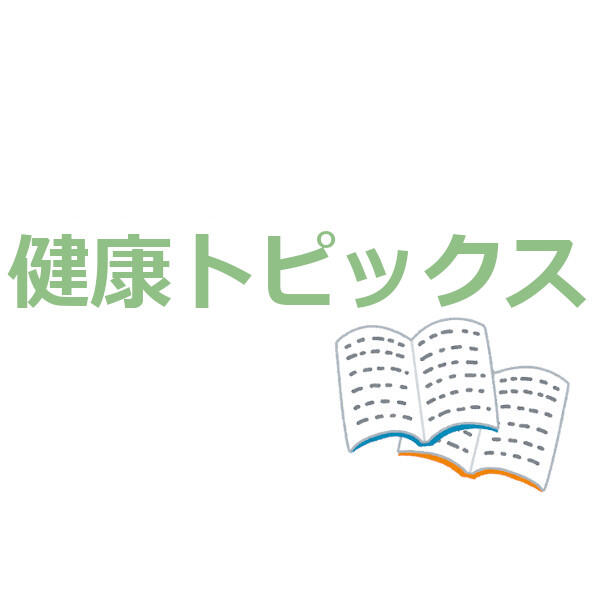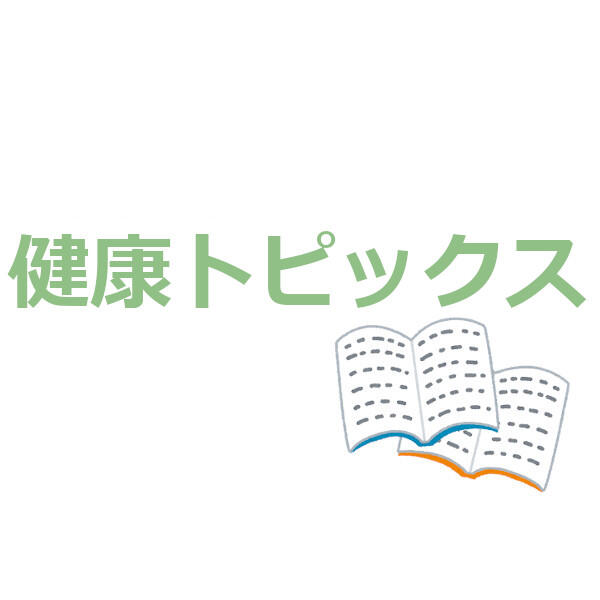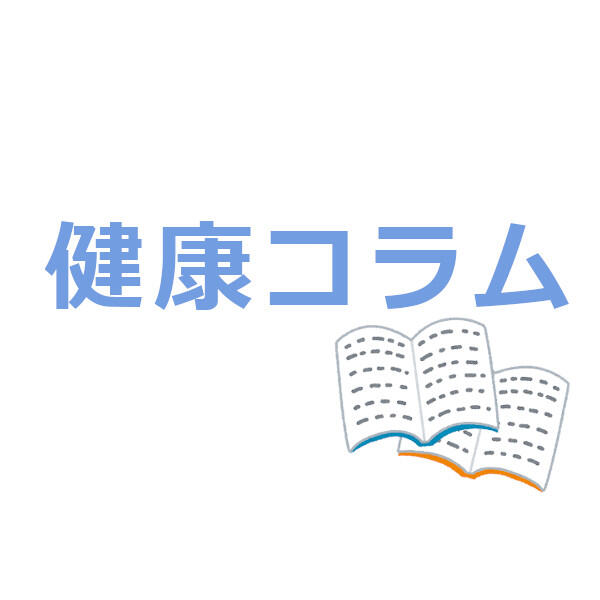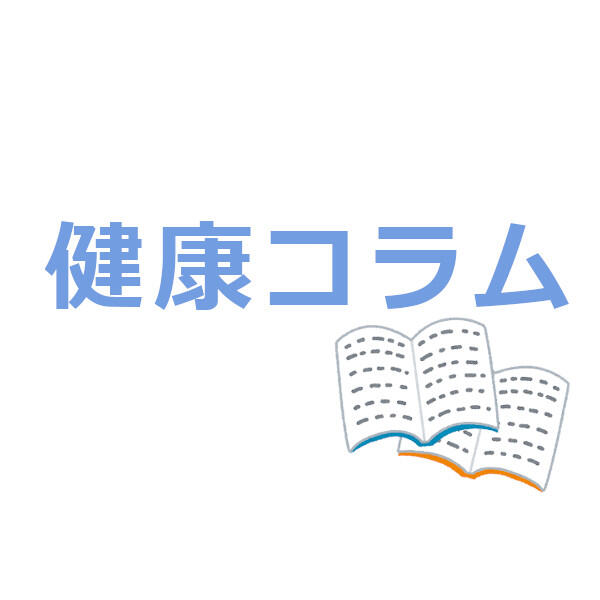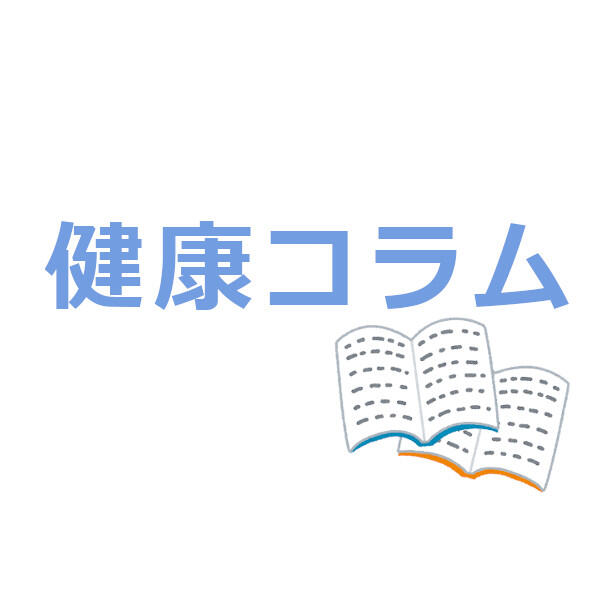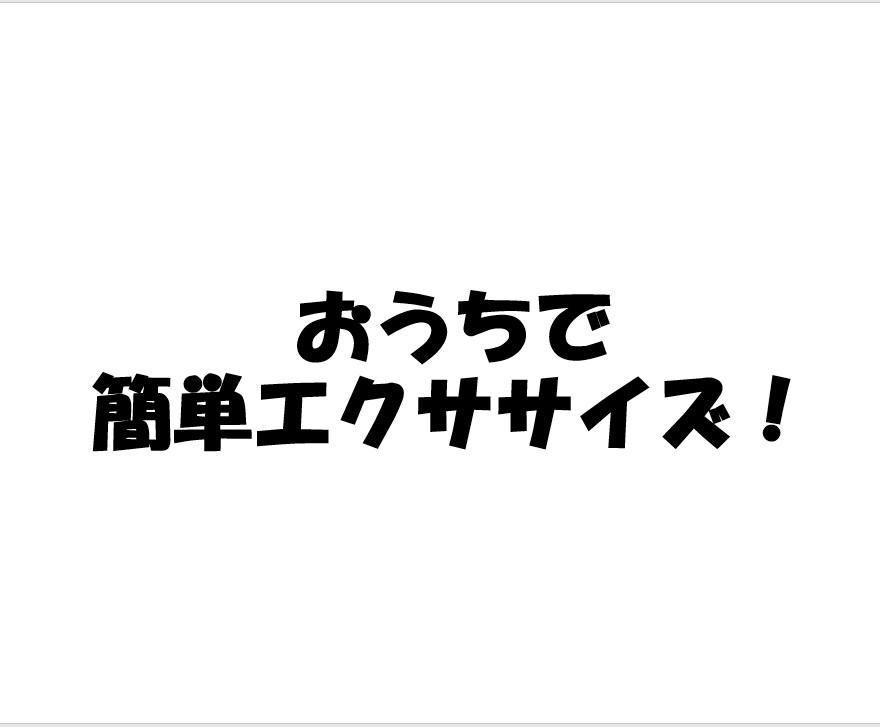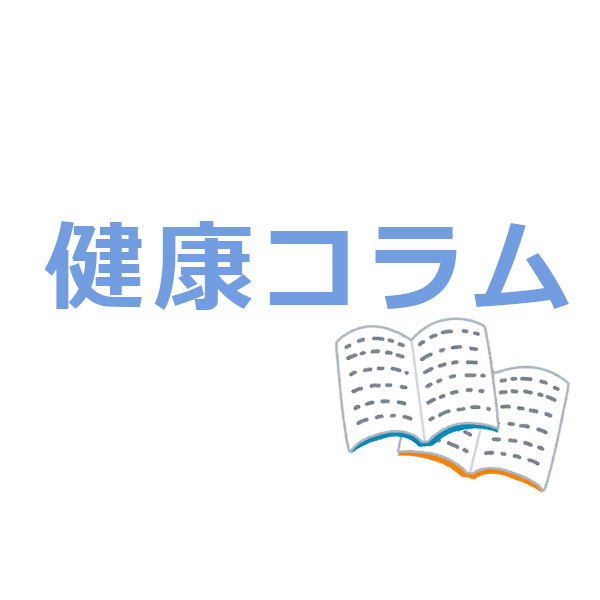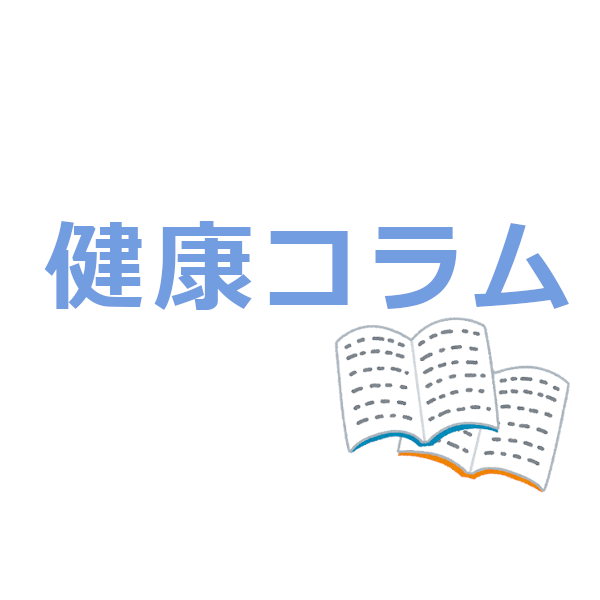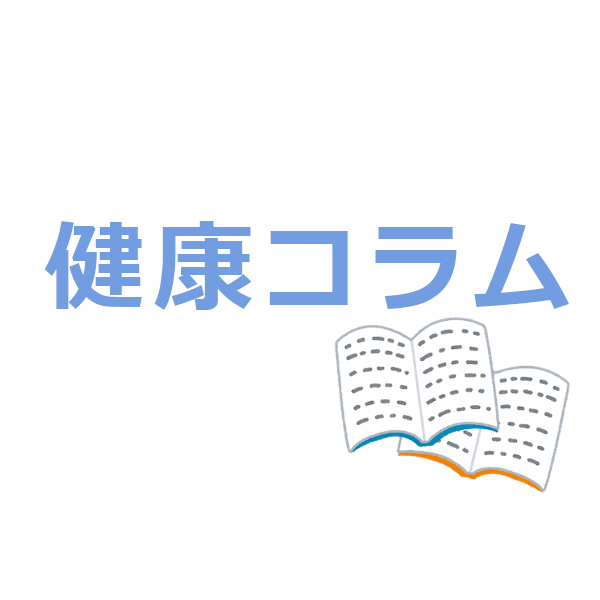毎日の健康習慣に役立つコラムや唐津市のお得な情報をお届けします!

健康維持と病気の予防には、適切な食事と運動に加え、睡眠が重要です。睡眠は、心身の疲れを癒し身体機能を回復させ、免疫やホルモンの働きを整えるなど重要な役割を担っています。
日本人の睡眠不足
OECD(経済協力開発機構)の調査(2014年)では、日本人の平均睡眠時間は、韓国に次いで2番目に短い7時間43分。厚生労働省の「国民健康・栄養調査」によると、睡眠時間が6時間未満の成人は約4割で過去10年間増加しています。さらに、英国のシンクタンクによると、日本の睡眠不足による年間の経済損失は、日本のGDPの2.92%にものぼる約15.7兆円(1380億ドル)。日本人の多くが睡眠不足や睡眠障害を抱えているだけでなく、健康経営の視点からも課題となっています。
いま「睡眠負債」が注目されています
「睡眠負債」とは、睡眠不足が積み重なることにより、疲れが蓄積して日常生活の質が低下し、病気のリスクが高い状態を指します。いわば、気づかないうちに膨れ上がっていく「眠りの借金」ともいえるでしょう。メディア等で取り上げられたこともあり、この考え方が注目されるようになりました。毎日の疲れを十分にリセットできず、脳や体に疲労が蓄積して疲れやすくなるため、運動量の減少にもつながり、体にさまざまな悪影響を及ぼします。必要な睡眠がとれない日が続くと、負債は蓄積する一方です。以下の項目に1つでも当てはまる場合、睡眠負債がある可能性も。睡眠負債を返済するために、生活習慣を見直し自分の睡眠についてしっかり把握しましょう。
□ 集中力が持続しない
□ 昼間に強い眠気を感じることがある
□ あまり寝つきがよくない
□ 朝、すっきり起きられない
□ 休日に、つい寝だめをしてしまう
睡眠の質を高める10のポイント
健康的な睡眠を確保するためには、起床、食事、就床などの規則正しい生活リズムが重要です。ちょっとした生活習慣の見直しによって、睡眠の質を高めることができます。
(1) 体内時計をととのえる
眠りを促すホルモン・メラトニンの分泌リズムが調節され、毎日決まった時間に自然な眠気を感じられるようになります。起床したらカーテンを開けて日光を浴びる、朝、昼、夕の食事を毎日同じ時刻にとるなど、体のリズムをキープするよう心がけましょう。
(2) 「パワーナップ」する
「パワーナップ」(power-nap)とは、短時間の昼寝(仮眠)のこと。足りない睡眠を補い、作業効率などをアップさせると考えられ、海外の企業や学校などでも推奨されています。夜の睡眠に影響を与えないよう、12〜15時に15〜30分程度の昼寝をしましょう。
(3) 午後はカフェインを控える
カフェインの半減期(体内での最高濃度が半分になる状態)は4〜6時間程ですが、完全に消失するには10時間以上必要です。午後はカフェイン入りの飲料を控えましょう。
(4) 寝る前に深酒はしない
アルコールは、中途覚醒(睡眠の途中で起きてしまう状態)をもたらし、睡眠の質を低下させます。アルコールはほどほどにしましょう。
(5) 入浴で深部体温を調節する
入眠時は手足の皮膚の血管が拡がり、体内より手足の温度が相対的に高い状態。睡眠中は手足から熱が外に逃げていくことで、深部温度(体内部の温度)が下がります。深部体温のコントロールのために、入浴を上手に利用しましょう。※入浴後の深部体温が下がり始めるまでに約90分かかるため、寝る前の熱いお風呂は避けましょう。
(6) 睡眠スイッチをオンに
寝る前のルーティン(決まりごと)をつくると、自然に体がリラックスして、睡眠モードに切り替わりやすいといわれています。「いつものパジャマに着替える」「決まった音楽を聴く」「決まった香りを嗅ぐ」など、毎日のルーティンを決めましょう。
(7) 就寝前1時間は「スマホ断ち」
PCやスマホのブルーライトは、睡眠障害の原因に。ブルーライトをカットするだけでなく、就寝の1時間前からはスマホを操作しないようにしましょう。
(8) 瞑想や呼吸法を活用
自律神経のバランスが乱れ、交感神経の働きが亢進していると、寝つきが悪くなります。瞑想やヨーガ(ヨガ)、ストレス対策として知られるマインドフルネスの呼吸法は、交感神経と副交感神経のバランスを整え、不眠症対策にも有効です。
(9) アロマセラピー(芳香療法)で睡眠対策
さまざまな植物由来のエッセンシャルオイル(精油)の香りによる体調の改善が報告されています。不眠症・睡眠障害のために最もよく用いられるのは、ラベンダー精油。自分に合ったアロマセラピー製品を選びましょう。
(10) 睡眠の質を改善する機能性食品成分の摂取
睡眠の質を改善する機能性食品成分として、欧米ではハーブのバレリアン(セイヨウカノコソウ)が知られています。また、健康食品では、快適な睡眠をサポートする成分としてラクティウム(牛乳由来の成分)やクワンソウエキス(沖縄のハーブ)などがあり、気分をリラックスさせる働きかけのある成分としては、緑茶に含まれるアミノ酸のテアニン、発芽玄米などに含まれるギャバなどがあります。これらの成分は、サプリメント(いわゆる健康食品)にも用いられていますので、有効的に活用しましょう。
睡眠の質を高めるために、自分に合う方法を試してみてはいかがでしょうか。