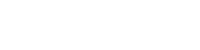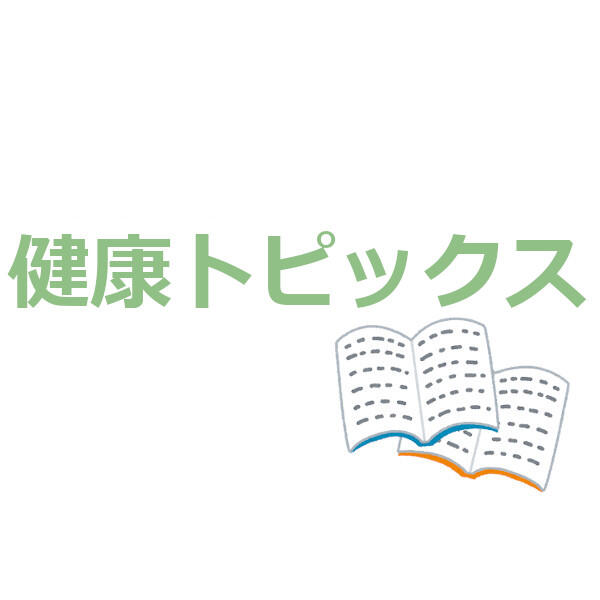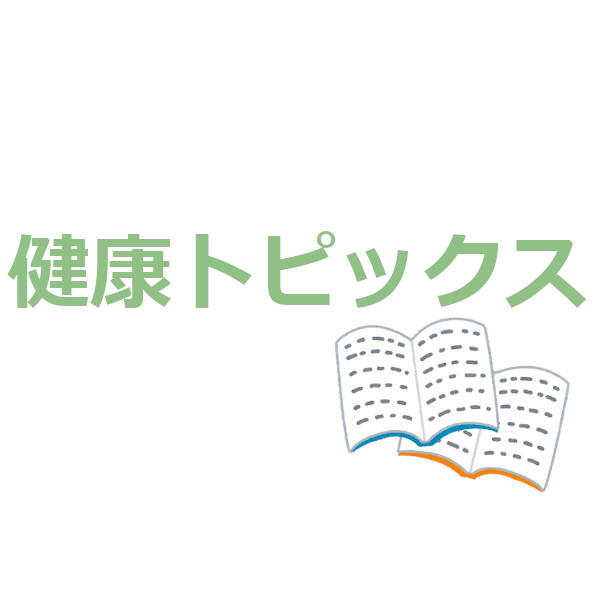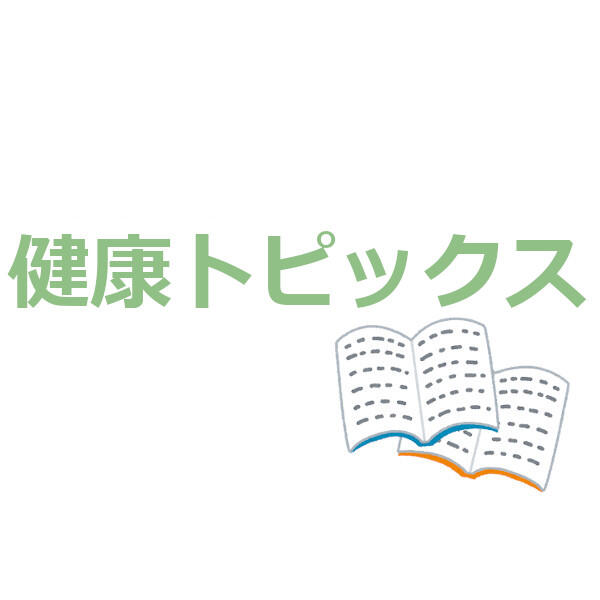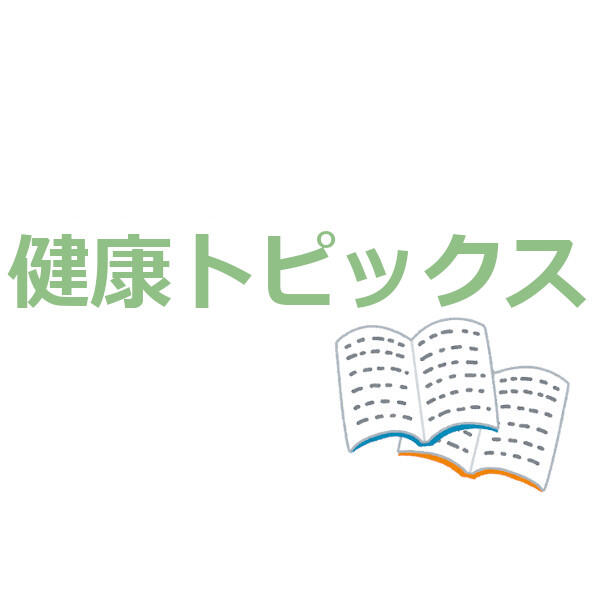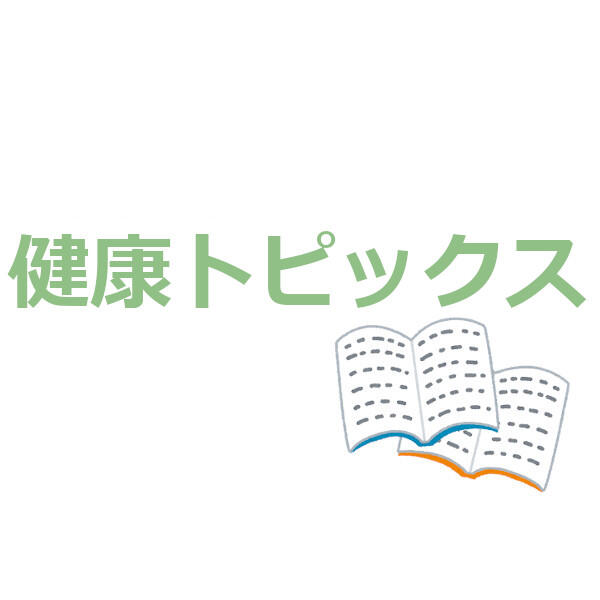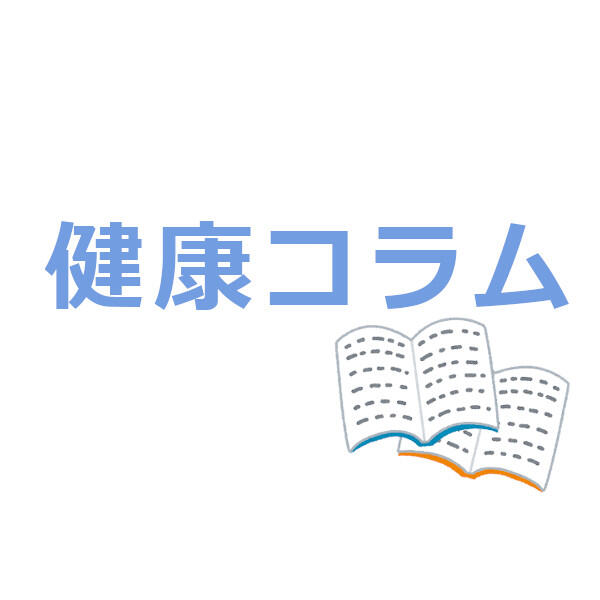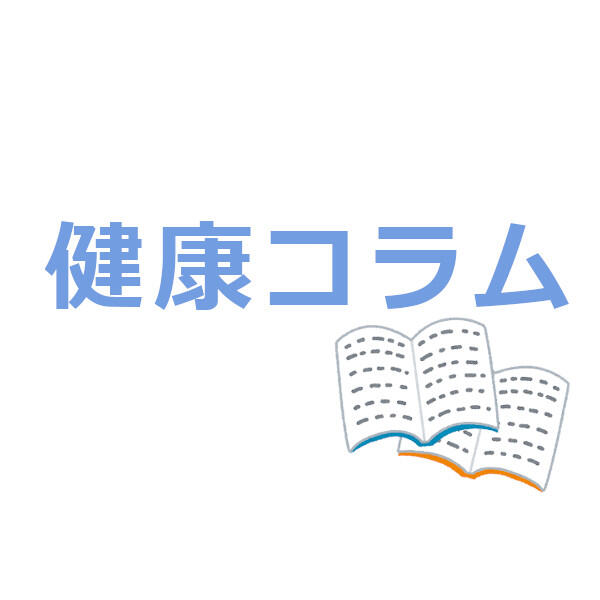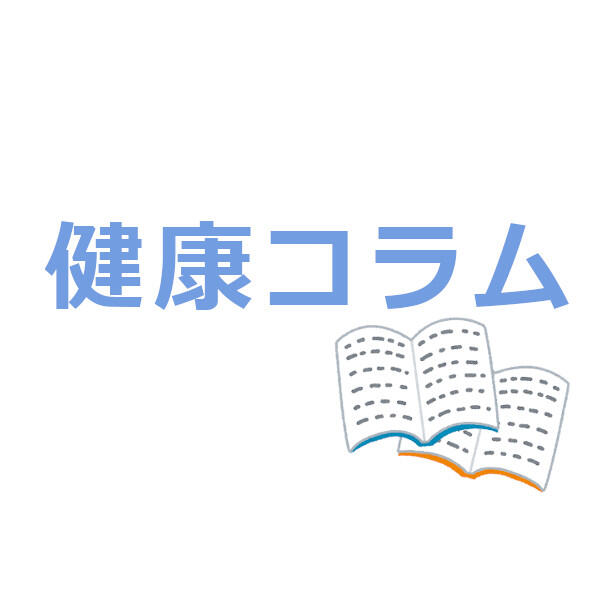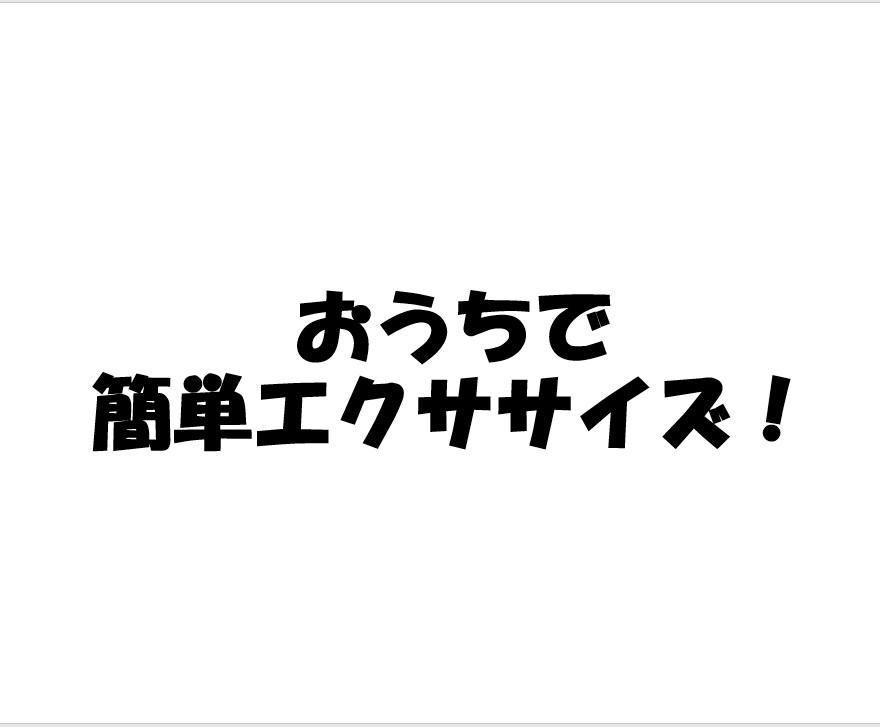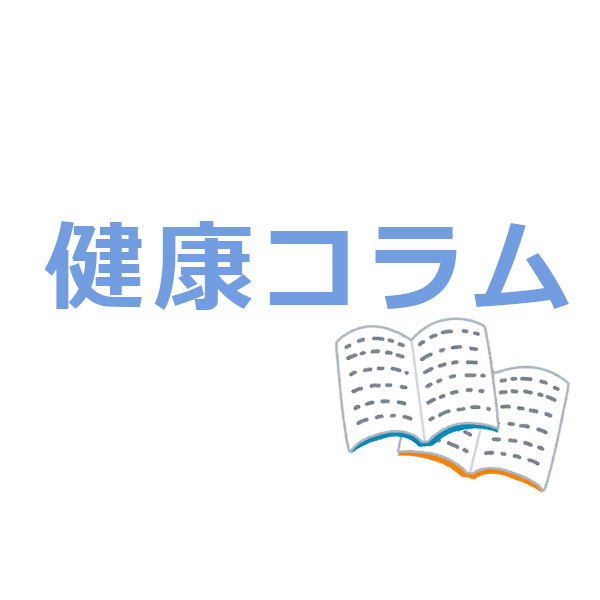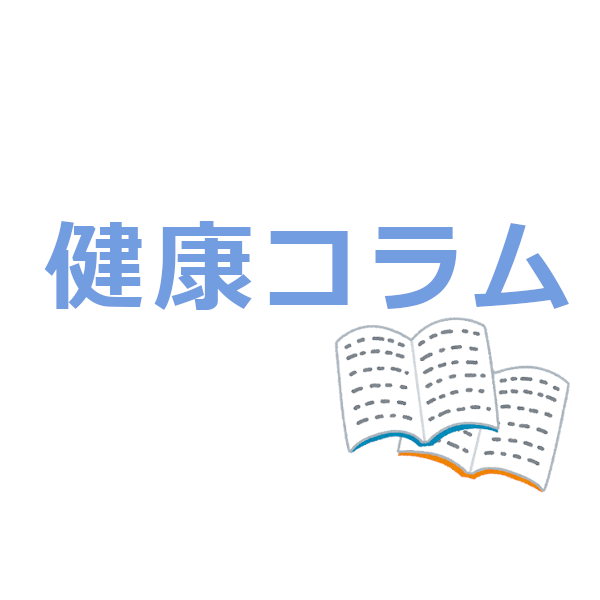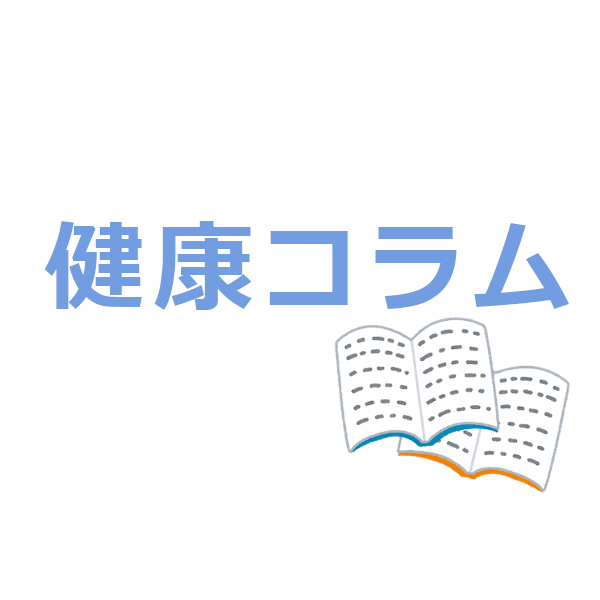毎日の健康習慣に役立つコラムや唐津市のお得な情報をお届けします!

最新の食事摂取基準では、ビタミンDの摂取基準が引き上げられました(日本人の食事摂取基準(2020年版))。最新の研究ではビタミンDの多彩な働きが明らかになっていますが、日本の摂取基準は、米国などの基準の半分程度。現在、日本ではビタミンD不足が懸念されています。
生活習慣病や転倒・骨折の予防にビタミンD
ビタミンDは、カルシウムの吸収を促進し、骨や歯の健康維持に働きます。また、ビタミンDやカルシウムが不足すると、骨粗鬆症の原因になります。
最新の研究では、ビタミンDが筋肉にも働き、高齢者の転倒・骨折を予防することがわかっています。さらに、免疫調節や抗炎症などの作用もあり、風邪の予防、がんや糖尿病などの生活習慣病や、線維筋痛症といった難治性疾患への有用性も示されています。
日光浴だけでは足りない?
現在、日本の子ども、若年女性、高齢者のビタミンD不足が顕著になっており、ビタミンD不足が原因の子どものくる病、高齢者の転倒・骨折や骨粗鬆症が増加しています。このような現状を踏まえて、「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、ビタミンDの摂取目安量が引き上げられました。
ビタミンDの1日当たりの摂取目安量
2015年版 5.5㎍(220IU)⇒ 2020年版 8.5㎍(340IU)
※18歳以上の場合。※IU…生体に対する効力を表す国際単位。1㎍=40IU。
ただし、この程度の引き上げでは不十分であり、ビタミンD不足に伴う課題解決は困難です。これに対して、アメリカの基準では、シニア層の推奨量が日本の2倍以上、1日あたり20〜25㎍(800〜1000IU)に設定されています。
なお、ビタミンDは日光により皮膚でも合成されるため、今回の食事摂取基準では、「適度な日光浴」「日照時間を考慮」などの脚注が入っています。しかし、高齢者の熱中症リスク、紫外線による皮膚や目への障害、女性の日焼け止めの使用状況を考えると、日光浴だけでなく、食事などからの摂取も重要です。
これまでの多くの研究によって、ビタミンDサプリメントの有用性を示すエビデンスが確立しています。
【米国国立骨粗鬆症財団(NOF)】
1日当たりの目安量
50歳まで 10-20μg(400-800 IU)
50歳以上 20-25μg(800-1,000 IU)
【米国国立保健研究所(NIH)/栄養補助食品室(ODS)】
【米国科学アカデミー(NAS)/全米医学アカデミー】
1日当たりの推奨量RDA(日)
19〜70歳まで 15μg(600 IU)
70歳超 20μg(800 IU)
高齢者の多くはビタミンD不足
高齢者は、皮膚のビタミンDを作る働きが低下していること、屋内で過ごす時間が長くなることなどから、ビタミンDが不足しやすくなります。ビタミンDの不足は、骨粗鬆症だけではなく、筋肉の働きにも影響するため、転倒・骨折のリスクが高くなります。日本人女性では、転倒・骨折がフレイル(虚弱)の主な原因となり、要介護・要支援の状態をもたらします。さらに、糖尿病などの生活習慣病でも、ビタミンD不足との関連が知られています。フレイルを予防し、健康寿命を延伸するために、ビタミンDの摂取が大切です。
あてはまったら、ビタミンDを積極的に摂るように心掛けましょう!
☑高齢である
☑夏はあまり外出しない
☑日焼け止めを使用する
☑魚や卵、きのこをあまり食べない